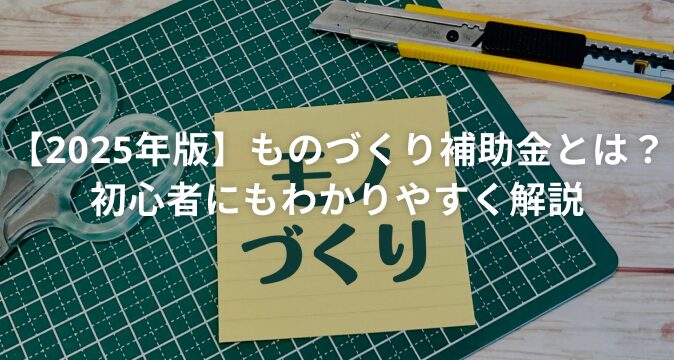
【2025年版】ものづくり補助金とは?初心者にもわかりやすく解説
「ものづくり補助金の申請方法がわからない」
「自分の業種でも使えるのか知りたい」
このようなお悩みはありませんか?
ものづくり補助金は、中小企業の設備投資や新商品開発を支援する制度です。2025年からは収益納付義務が撤廃され、最大4,000万円まで受給可能です。
そこで、この記事では、ものづくり補助金の活用を検討している方へ向けて、令和7年の最新制度や申請方法について解説します。申請準備の参考として、ぜひ最後までお読みください。
ものづくり補助金とは【令和7年最新版】
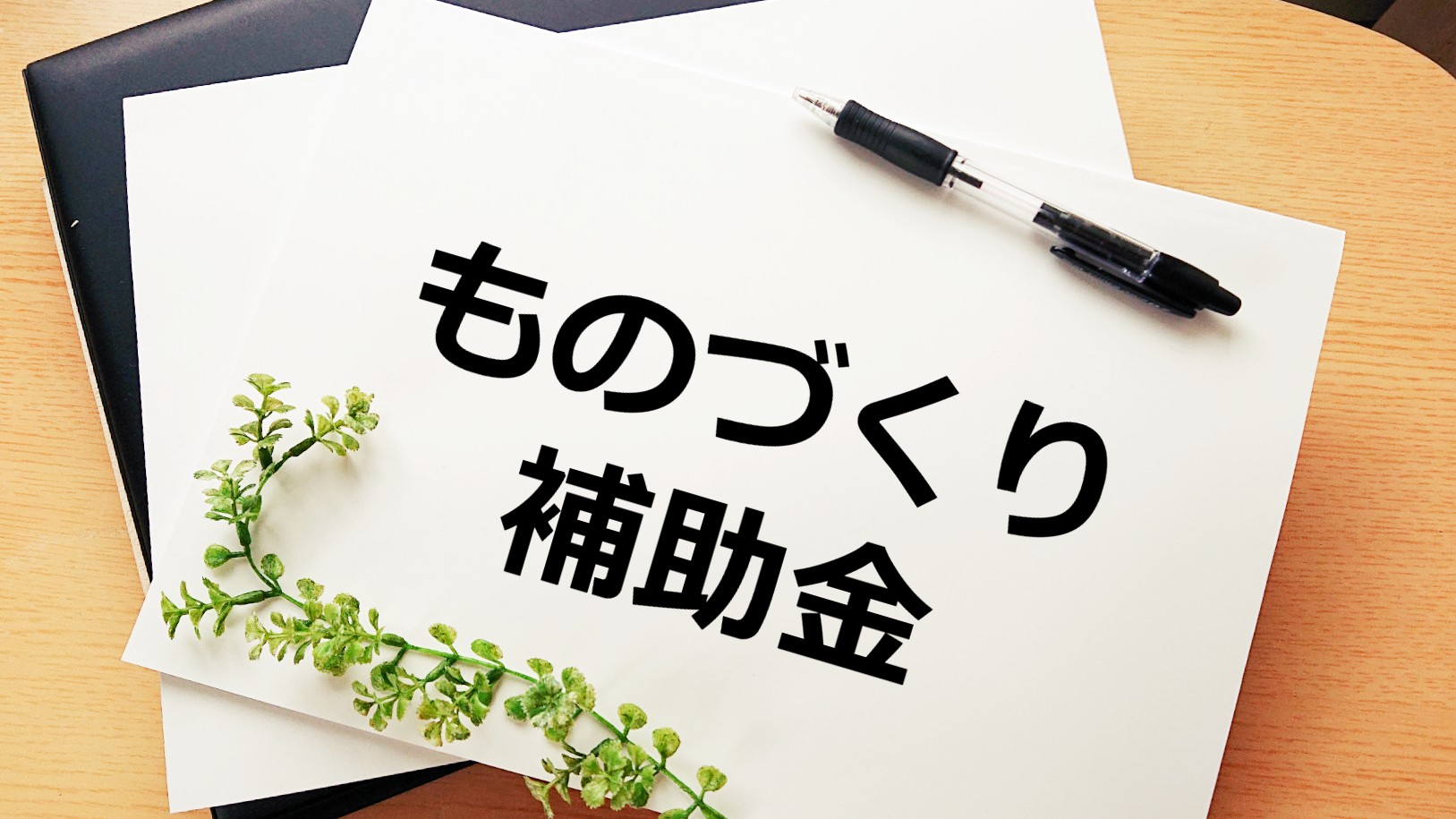
ものづくり補助金は、国が中小企業や個人事業主に支給する補助金制度です。新しい設備の導入やシステム開発などの設備投資に活用できます。令和7年度には制度が大きく変わり、これまでよりも使いやすくなりました。
2025年の主なポイントには下記の3つがあります。
・制度の目的と概要
・2025年の主な変更点
・補助金の仕組み
それぞれ詳しく説明していきましょう。
制度の目的と概要
ものづくり補助金の目的は「会社の売上を増やして、働く人の給料をアップすること」です。
正式な名前は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。国の機関である中小企業庁が運営している制度です。この補助金では、新しい商品を作ったり、お客さんに喜ばれるサービスを始めたりするために必要なお金を応援してくれます。
例えば、パン屋さんが新しいオーブンを買うお金や、美容院が予約システムを作るお金などがもらえます。対象になるのは中小企業や小さな会社、個人で商売をしている人たちです。工場だけでなく、お店やサービス業、建設業なども申込めます。
参考:全国中小企業団体中央会|ものづくり補助金総合サイト
2025年の主な変更点
2025年のものづくり補助金では、事業者が使いやすくなるように4つの大きな変更がありました。
主な変更点は下記の通りです。
・収益納付義務の撤廃
・申請枠の統合
・最低賃金引上げ特例の新設
・補助上限額の拡充
これらの変更は、中小企業の成長をより強力に支援するために実施されました。
一番大きな変更は「お金を返さなくてよくなった」ことです。前までは補助金をもらった後に儲かったら、その分の一部を国に返す決まりがありました。しかし2025年からはこの決まりがなくなりました。また、申込みの種類が複数あったものが2つに減って、手続きが簡単になっています。さらに「給料をたくさん上げる会社への特別サービス」も始まり、働く人の給料を大幅に上げる会社は補助金の割合が半分から3分の2に増えます。補助金の上限額が最大4,000万円まで引き上げられました。
参考:全国中小企業団体中央会|ものづくり補助金総合サイト
補助金の仕組み
ものづくり補助金は、先にお金を使ってから後で補助金をもらう「後払い」の制度です。
申込みから補助金をもらうまでの流れは次のようになります。
1.申込み
2.審査
3.合格発表
4.正式な手続き
5.事業を実行
6.報告書提出
7.補助金
補助金の割合は、基本的に投資額の半分が補助されます。小さな会社や個人事業主の場合は3分の2になります。
また、合格した人は3年から5年間の計画を実行する必要があります。売上を毎年3%以上増やし、給料の総額を毎年2%以上増やすという目標があります。この目標を達成できなかった場合、一部または全額の補助金返還を求められることがあります。
そのため、しっかりとした計画を立てることが大切です。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
ものづくり補助金の対象事業者

ものづくり補助金の対象事業者には大きく2つのグループがあります。
・中小企業・小規模事業者
・個人事業主
一方で、大きな会社や特定の条件に当てはまらない事業者は対象外となります。自分が申し込めるかどうかを確認していきましょう。
中小企業の定義と要件
中小企業がものづくり補助金に申込むには、業種ごとに決められた基準を満たす必要があります。
中小企業基本法に基づいて、従業員数と資本金のどちらか一方の条件をクリアすれば対象となります。この基準は業種によって異なるため、まずは自分の会社がどの業種に当てはまるかを確認することが大切です。
| 業種 | 従業員数 | 資本金 |
| 製造業・建設業・運輸業 | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
また、申請時点で実際に事業を行っていることが条件となります。法人の場合は法人登記を完了していること、個人事業主の場合は税務署に開業届を提出済みであることが必要です。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
個人事業主の対象条件
個人事業主もものづくり補助金に申込むことができます。
個人事業主が申込む場合の条件は比較的シンプルです。税務署に開業届を提出していて、実際に事業活動を行っていることが基本的な要件となります。創業したばかりの個人事業主でも申込めるため、新しくビジネスを始めた人にとっても利用しやすい制度です。
ただし、個人事業主の場合でも中小企業と同じように、付加価値額や給与支給総額の成長目標を達成する必要があります。1人で事業を行っている場合は給与支給総額の計算方法が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。また、申請時には直近の確定申告書の提出が求められます。
参考:全国中小企業団体中央会|よくあるご質問
対象外となる事業者
大企業や特定の条件に当てはまる事業者は、ものづくり補助金の対象外となります。
対象外となる主なケースは下記の通りです。
・中小企業の基準を超える大企業
・国や地方公共団体が運営する機関
・宗教法人や政治団体
また、暴力団関係者や反社会的勢力との関わりがある事業者も対象外となります。
さらに、過去にものづくり補助金で不正行為を行った事業者や、補助金の返還義務を果たしていない事業者も申込みを制限される場合があります。NPO法人や一般社団法人については、営利活動を行っていて税法上の収益事業を実施していれば申込み可能です。申込み前に自分の事業者種別が対象になるかどうかを必ず確認しましょう。
ものづくり補助金の申請条件

ものづくり補助金に申込むには、3つの重要な条件をクリアする必要があります。
・付加価値額の成長率要件
・賃上げ目標の達成義務
・事業計画期間の設定
これらの条件を満たさない場合は補助金を返さなければいけないので、申込み前にしっかりと理解しておきましょう。
付加価値額の成長率要件
付加価値額を毎年3%以上増やすことが、ものづくり補助金の基本的な条件です。
付加価値額とは、会社がどれだけ価値を生み出したかを表す数字のことです。計算方法は「営業利益+人件費+減価償却費」となります。営業利益は会社の儲け、人件費は給料の総額、減価償却費は機械や設備の価値が減った分のお金のことです。
この付加価値額を事業計画期間中に年平均で3%以上増やし続ける必要があります。例えば、今年の付加価値額が1,000万円だった場合、来年は1,030万円以上にしなければいけません。もしこの目標を達成できなかった場合は、受け取った補助金を国に返還する義務が発生します。そのため、実現可能な計画を立てることが非常に重要です。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
賃上げ目標の達成義務
働く人の給料を毎年2%以上増やすことも、ものづくり補助金の必須条件です。
賃上げ目標には2つの方法があり、どちらか一方を選んで達成すれば条件をクリアできます。
・給与支給総額を増やす方法
・1人当たり給与を増やす方法
さらに2025年からは特例制度も新設され、より多くの補助金を受け取るチャンスが広がりました。
給与支給総額を増やす方法
会社全体の給料の総額を毎年2%以上増やす方法です。
全従業員の給料を合計した金額を、事業計画期間中に年平均成長率2%以上で増加させる必要があります。例えば、今年の給料総額が5,000万円だった場合、来年は5,100万円以上にしなければいけません。
1人当たり給与を増やす方法
1人当たりの給料を、その地域の最低賃金の上昇率以上に増やす方法です。
事業を実施する都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上に、従業員1人当たりの給与を増加させる必要があります。この方法は従業員数が少ない会社や個人事業主にとって選びやすい選択肢となります。
最低賃金引上げ特例
地域の最低賃金より50円以上高い給料をもらっている従業員が全体の30%以上いる会社は、補助金の割合が半分から3分の2に増えます。この特例を活用すれば、より多くの補助金を受け取れるため、積極的な賃上げを検討してみましょう。
事業計画期間の設定
ものづくり補助金では、3年から5年間の事業計画を作って実行する必要があります。
事業計画期間は自分で3年、4年、5年のうちから選べます。この期間中は、先ほど説明した付加価値額と賃上げの目標を毎年達成し続けなければいけません。また、毎年「事業化状況報告書」という書類を提出して、計画通りに進んでいるかを国に報告する義務もあります。
計画期間が長いほど目標達成のチャンスは増えますが、その分長期間にわたって目標達成が求められます。
短い期間を選べば早く要件から外れますが、急激な成長が求められるため難易度が上がります。
自分の事業の特性や成長の見込みを考えて、無理のない計画期間を選ぶことが大切です。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
ものづくり補助金の申請枠と補助額【2025年更新】

2025年のものづくり補助金では、申請枠が2つに統合されました。
・製品・サービス高付加価値化枠
・グローバル枠
それぞれの枠で補助額が異なり、さらに大幅賃上げ特例を活用すれば上限額を引き上げることができます。
自分の事業に合った枠を選んで申込みましょう。
製品・サービス高付加価値化枠の補助額
製品・サービス高付加価値化枠では、従業員数によって補助額の上限が決まります。
この枠は新しい商品やサービスを開発して、会社の売上アップを目指す事業に使える補助金です。従業員数が多い会社ほど、より多くの補助金をもらうことができる仕組みになっています。補助率は基本的に2分の1で、小規模事業者の場合は3分の2になります。
| 従業員数 | 補助上限額 |
| 5人以下 | 750万円 |
| 6~20人 | 1,000万円 |
| 21~50人 | 1,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 |
2025年から従業員数21人以上の区分が細分化され、より多くの補助金を受け取れるようになりました。特に従業員数51人以上の会社では、大幅に上限額が引き上げられています。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
グローバル枠の補助額
グローバル枠では、従業員数に関係なく一律の補助額が設定されています。
この枠は海外展開や輸出を目指す事業に使える補助金です。海外のお客さんに商品を売ったり、海外に工場を作ったりする計画がある会社が申込めます。補助率は1/2で、小規模事業者の場合は2/3になります。
グローバル枠の補助上限額は3,000万円となっています。製品・サービス高付加価値化枠と比べて、従業員数が少ない会社でも高額な補助金を狙えることが特徴です。
ただし、海外展開に関する具体的な計画と実績が求められるため、申請の難易度は高くなります。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
大幅賃上げ特例の上限額
大幅賃上げ特例を活用すると、どちらの枠でも補助上限額を引き上げられます。
大幅賃上げ特例とは、働く人の給料を大きく上げる会社に対して、補助金の上限額を増やす制度です。この特例を受けるには、事業計画期間中に給与支給総額の年平均成長率を6%以上にする必要があります。通常の賃上げ要件が2%以上なので、3倍の成長が求められることになります。
特例を活用した場合の上限額の増加幅は下記の通りです。
| 対象枠・従業員数 | 増額幅 | 特例適用後の上限額 |
| 製品・サービス高付加価値化枠 5人以下 | 100万円 | 850万円 |
| 製品・サービス高付加価値化枠 6~20人 | 250万円 | 1,250万円 |
| 製品・サービス高付加価値化枠 21~50人 | 1,000万円 | 2,500万円 |
| 製品・サービス高付加価値化枠 51人以上 | 1,000万円 | 3,500万円 |
| グローバル枠 | 1,000万円 | 4,000万円 |
特に従業員数が多い会社では大幅な増額となるため、積極的な賃上げを検討している会社にとって魅力的な制度です。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
ものづくり補助金の対象経費

ものづくり補助金では、決められた種類の費用だけが補助の対象になります。
・機械装置・システム構築費
・技術導入費・専門家経費
・対象外となる経費
どの費用が補助対象になるかを事前に確認して、計画的に設備投資を進めることが重要です。
機械装置・システム構築費
機械装置・システム構築費は、ものづくり補助金で最も多く使われる経費の種類です。
この経費には新しい機械を買うお金やコンピューターシステムを作るお金が含まれます。例えば、工場で使う新しい製造機械、お店の会計システム、ホームページやアプリの開発費用などが対象となります。ただし、すでに使っている古い機械と同じ性能の機械に買い替える場合は対象外になります。
対象となる主な費用は下記の通りです。
・事業に必要な機械・装置の購入費
・専用ソフトウェアの購入・開発費
・クラウドサービスの初期導入費
・運搬費・据付費
購入する機械やシステムは、新しい商品やサービスを作るために必要で、これまでにない革新的な取り組みに使われるものでなければいけません。また、1件当たり50万円以上の費用でないと補助対象になりません。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
技術導入費・専門家経費
技術導入費・専門家経費は、新しい技術を学んだり専門家に相談したりするために使う費用です。
技術導入費には、特許権や実用新案権の取得費用、他の会社が持っている技術を使うための費用などが含まれます。専門家経費には、コンサルタントへの相談料、技術指導を受けるための費用、研修・講習の参加費などが含まれます。これらの費用は、自分の会社だけでは解決できない技術的な課題を解決するために使われます。
対象となる経費の種類は下記の通りです。
技術導入費
・知的財産権の導入に要する経費
・他社が持つ技術やノウハウの導入費
・外国技術の導入費
専門家経費
・技術指導・助言を受けるための費用
・研修・講習の受講費
・コンサルティング費用
ただし、自分の会社の従業員に支払う給料や、日常的な業務で発生する費用は対象外となります。また、専門家経費は補助対象経費全体の3分の1を超えることはできません。
対象外となる経費
ものづくり補助金では、日常的な業務に関する費用や個人的な用途に使える費用は対象外となります。 対象外となる主な経費には、従業員の給料、事務所の家賃、光熱費、消耗品費、既存設備の修理費などがあります。これらは会社の普通の運営に必要な費用であり、新しい取り組みのための投資ではないため補助対象になりません。また、汎用的なパソコンや事務用品、自動車なども対象外です。
| 対象外の経費 | 理由 |
| 従業員の給料・賞与 | 人件費は対象外のため |
| 事務所・工場の家賃 | 通常の運営費のため |
| 光熱費・通信費 | 日常的な経費のため |
| 汎用的なパソコン・プリンター | 専用設備でないため |
| 自動車・トラック | 汎用品のため |
さらに、補助事業が完了する前に購入した設備も対象外となります。必ず採択通知を受けて交付決定を受けてから購入を始めるようにしましょう。
ものづくり補助金の申請方法【2025年版】

ものづくり補助金の申請は、すべてインターネットを使った電子申請で行います。
・電子申請の手順
・必要書類の準備
・事業計画書の作成方法
申請締切の直前は非常に混雑するため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
電子申請の手順
ものづくり補助金の申請は、jGrantsという電子申請システムを使って行います。
申請を始める前に、まずGビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。このアカウントの取得には2週間程度かかる場合があるため、申請を考えている人は早めに手続きを始めましょう。GビズIDは国が運営する法人向けの共通IDで、さまざまな行政手続きに使えます。
電子申請は下記の5つのステップで進めます。
ステップ1:事前準備
GビズIDプライムアカウントを取得し、jGrantsにログインできることを確認します。必要書類をすべてPDF形式で準備しておきましょう。
ステップ2:システムへのログイン
jGrantsの電子申請システムにGビズIDを使ってログインします。ものづくり補助金の申請画面を開いて、申請を開始しましょう。
ステップ3:申請情報の入力
会社の基本情報、事業計画の内容、補助金額などを画面に直接入力します。文字数制限があるため、要点を整理して入力してください。
ステップ4:書類のアップロード
準備したPDF書類をシステムにアップロードします。ファイルサイズの制限があるため、事前に確認しておきましょう。
ステップ5:最終確認と提出
入力内容と添付書類をすべて確認し、間違いがなければ申請を提出します。提出後は修正できないため、慎重にチェックしてください。
申請は24時間いつでも可能ですが、締切日の17時までに完了させる必要があります。システムトラブルに備えて、締切の数日前には申請を完了させておくことをおすすめします。
必要書類の準備
ものづくり補助金の申請には、会社の状況や申請内容に応じてさまざまな書類が必要になります。
申請に必要な書類は、申請者の種類によって異なります。基本的に必須となる書類と、特定の条件に該当する場合のみ必要な書類があります。すべての書類はPDF形式でアップロードする必要があるため、事前にスキャンやPDF変換の準備をしておきましょう。
必要書類は下記のように分かれます。
法人の場合(必須書類)
・事業計画書(電子申請システムに直接入力)
・直近2期分の決算書類(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細書など)
・法人税確定申告書の写し
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
個人事業主の場合(必須書類)
・事業計画書(電子申請システムに直接入力)
・直近2年分の所得税確定申告書の写し
・開業届の写し
条件に応じて必要な書類
・従業員数を証明する書類(従業員がいる場合)
・一般事業主行動計画(従業員101人以上の場合のみ)
・加点項目に該当する証明書類(該当する場合のみ)
・海外展開に関する証明書類(グローバル枠申請の場合のみ)
創業1年未満の場合は決算書の代わりに収支予算書を提出し、創業1年以上2年未満の場合は1期分の決算書のみで申請可能です。
事業計画書の作成方法
事業計画書は、審査で最も重要な書類であり、採択されるかどうかを決める核となる部分です。
2025年からは事業計画書を電子申請システムに直接入力する方式に変更されました。文字数制限があるため、要点を絞ってわかりやすく書くことが重要です。事業計画書では、現在の課題、補助事業の目的、具体的な取り組み内容、期待される効果などを明確に説明する必要があります。
事業計画書に含めるべき主な内容は下記の通りです。
・現在の事業の概要と課題
・補助事業で取り組む内容
・導入する設備や技術の詳細
・事業実施後の効果と売上予測
・付加価値額と賃上げの具体的な計画など
特に「なぜその設備が必要なのか」「どのような効果が期待できるのか」を具体的な数字を使って説明することが大切です。また、自分の会社の強みや競合他社との違いも明確にして、審査員に事業の革新性をアピールしましょう。
参考:全国中小企業団体中央会|公募要領
ものづくり補助金の採択率を上げるポイント

ものづくり補助金の採択率は年によって変動しますが、直近では30%台となっています。
・審査基準のクリア方法
・加点項目の活用法
・よくある不採択理由
採択されるためには審査のポイントを理解し、計画的に申請書を作成することが重要です。
審査基準のクリア方法
ものづくり補助金の審査では、技術面・事業化面・政策面の3つの観点から評価されます。
この審査では「今までにない新しい取り組みかどうか」と「本当に売上アップにつながるかどうか」が厳しく判断されます。
単なる設備の買い替えや、他社と同じような商品開発では採択されにくくなっています。
審査基準をクリアするための重要なポイントは下記の通りです。
技術面の評価ポイント
・新製品・新サービスの革新的な内容
・競合他社との技術的な差別化
・課題解決に向けた具体的なアプローチ
事業化面の評価ポイント
・市場ニーズの明確な分析9
・売上予測の根拠と実現可能性
・事業化までのスケジュールの妥当性
政策面の評価ポイント
・地域経済への貢献
・雇用創出への期待
・付加価値額と賃上げ目標の妥当性
加点項目の活用法
加点項目を上手に活用すると、審査で有利になり採択率を高められます。
加点項目とは、基本的な審査項目に加えて追加で評価される項目のことです。これらの項目に該当する場合は、審査の際に点数が上乗せされるため、採択の可能性が高くなります。2025年の主な加点項目には、賃上げへの取り組み、地域経済への貢献、事業承継などがあります。
該当する加点項目があれば、必要な証明書類を準備して積極的に活用しましょう。
主な加点項目とその活用方法は下記の通りです。
賃上げ加点
・給与支給総額を年率平均2%以上増加させる計画
・最低賃金+50円以上の従業員が30%以上いる場合の特例
地域未来牽引企業
・経済産業省が認定する地域の中核企業としての登録
・地域経済の活性化に貢献する事業計画
事業承継加点
・代表者の交代を伴う事業承継を行う場合
・事業承継を契機とした新しい取り組み
その他の加点項目
・創業・第二創業から5年以内の場合
・パートナーシップ構築宣言を行っている場合
・女性活躍推進法に基づく認定を受けている場合
よくある不採択理由
不採択となる申請には、共通したパターンがいくつかあります。
最も多い不採択理由が「革新性の不足」です。既存の商品やサービスとの違いが明確でない場合や、単なる設備の更新に留まる場合は採択されません。
また「事業計画の実現可能性への疑問」もよくある不採択理由となっています。売上予測が楽観的すぎる場合や、具体的な根拠が示されていない場合は評価が下がります。
よくある不採択理由を下記にまとめました。下記の問題を避けるためには、公募要領をしっかりと読み込み、第三者の視点で事業計画を見直すことが大切です。可能であれば専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
計画内容に関する問題
・革新性や新規性が不十分
・競合他社との差別化が不明確
・単なる設備更新や汎用品の購入
事業化の見通しに関する問題
・市場分析が不十分
・売上予測の根拠が薄弱
・事業化スケジュールが非現実的
書類作成に関する問題
・事業計画書の記載内容が不十分
・必要書類の不備や提出漏れ
・数値計算のミスや矛盾
ものづくり補助金の2025年変更点

2025年のものづくり補助金では、事業者にとって大きなメリットとなる変更が実施されました。
・収益納付義務の撤廃
・申請枠の統合
・最低賃金引上げ特例の新設
これらの変更により、中小企業がより使いやすい制度に生まれ変わりました。
収益納付義務の撤廃
2025年から、補助事業で利益が出ても国にお金を返す必要がなくなりました。
従来の制度では「収益納付」という仕組みがありました。これは補助金をもらった事業で儲かった場合、その利益の一部または全部を国に返さなければいけない制度でした。
しかし2025年からはこの義務が完全になくなりました。補助金をもらって事業が成功し、どれだけ大きな利益が出ても返納する必要はありません。これにより事業者は安心して積極的な投資を行い、事業の成果をそのまま会社の成長に活用できるようになりました。中小企業庁は「中小企業の成長を加速させる観点から、財務当局と調整した結果」としてこの変更を発表しています。
申請枠の統合
2025年から申請枠が複数あったものから2つに統合され、申請手続きが簡単になりました。
2024年までは製品・サービス高付加価値化枠、DX枠、GX枠、グローバル枠、サプライチェーン強靭化枠など、複数の申請枠がありました。申請者はこれらの中から自分の事業に最も適した枠を選ぶ必要があり、どの枠を選べばよいか判断が難しい状況でした。
2025年からは下記の2つの枠に統合されました。
・製品・サービス高付加価値化枠:新しい商品やサービスの開発に使う
・グローバル枠:海外展開や輸出を目指す事業に使う
この統合により申請者は枠選びで迷うことが少なくなり、申請書類の作成も簡素化されました。どちらの枠を選ぶかは事業の内容で明確に判断できるため、申請への取り組みがしやすくなっています。
補助上限額の拡充
2025年から従業員規模別の補助上限額が大幅に引き上げられました。
特に従業員数が多い企業にとって大きなメリットとなる変更が実施されています。従来は従業員21人以上の区分が一律でしたが、2025年からは21〜50人と51人以上に細分化され、それぞれで上限額が大幅に増額されました。
主な変更内容は下記の通りです。
・従業員21~50人:1,250万円→1,500万円(250万円増額)
・従業員51人以上:1,250万円→2,500万円(1,250万円増額)
・グローバル枠:3,000万円→4,000万円(1,000万円増額)
特に従業員51人以上の企業では補助上限が倍額になり、大規模な設備投資に対応できるようになりました。これにより中堅企業でも積極的な設備投資を計画しやすくなっています。
最低賃金引上げ特例の新設(補助率向上+加点効果)
2025年から働く人の給料を積極的に上げる会社への特別な支援制度が始まりました。
この特例は「最低賃金引上げ特例」と呼ばれ、従業員の給料を地域の最低賃金より50円以上高く設定している会社が対象となります。
具体的には、最低賃金+50円以上の給料をもらっている従業員が全従業員の30%以上いる会社が条件を満たします。
この制度には2つの大きなメリットがあります。
・補助率の向上:中小企業の補助率1/2が2/3に向上(小規模事業者は元々2/3のため変更なし)
・審査時の加点:採択の可能性が高くなる
例えば、中小企業が1,000万円の設備投資を行う場合、通常なら500万円の補助金ですが、この特例を使えば約667万円の補助金を受け取ることができます。
小規模事業者の場合は、元々2/3の補助率のため補助率向上はありませんが、審査時の加点効果を受けることができます。
まとめ:令和7年度ものづくり補助金の活用戦略
令和7年度のものづくり補助金は、収益納付義務の撤廃や最低賃金引上げ特例の新設により、これまでで最も事業者にとって有利な制度となりました。
2025年の制度改正により事業者にとって改善されたポイントは下記の通りです。
・補助事業で利益が出ても返納不要
・申請枠が2つに統合されて手続きが簡単
・積極的な賃上げ企業には補助率が3分の2に向上
・最大4,000万円までの補助金が受給可能
申請を成功させるには、革新的な事業計画の作成、付加価値額と賃上げ目標の設定、加点項目の積極的な活用が重要です。現在進行中の20次公募は2025年7月25日が締切となっているため、申請を検討している場合は早めの準備が必要です。
ものづくり補助金は中小企業の成長を強力に支援する制度です。自社の課題解決と成長戦略に合わせて、積極的な活用を検討してみましょう。
