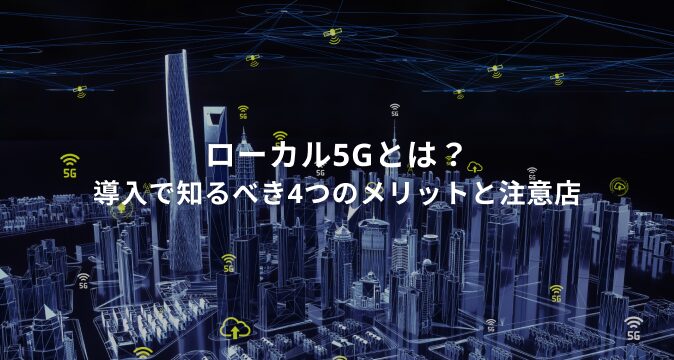
ローカル5Gとは?導入で知るべき4つのメリットと注意点
「ローカル5Gってどんな技術なの?」
「Wi-Fiとの違いがわからない」
「導入方法や免許取得が複雑で難しそう」
このようなお悩みはありませんか?
ローカル5Gは、企業が独自に構築する専用の5Gネットワークで、製造業のDXや医療現場の効率化に役立ちます。適切に導入することで、高いセキュリティと安定した高速通信が可能です。
そこで、この記事では、ローカル5G導入を検討している方へ向けて基本概念やメリット・デメリット、実際の導入事例について解説します。導入方法や免許取得の参考として、ぜひ最後までお読みください。
ローカル5Gとは?基本をわかりやすく解説

ローカル5Gとは、企業や自治体が独自に作る専用の5G通信網です。携帯電話会社の5Gとは別に、限られた場所だけで使える通信技術として注目されています。
ローカル5Gの基本について、下記の2つのポイントで解説していきます。
・ローカル5Gの定義と仕組み
・5Gの基本特徴
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ローカル5Gの定義と仕組み
ローカル5Gとは、企業や自治体が自分で基地局を設置して作る専用の5G通信網です。
国から免許を取得することで、専用の電波を使って通信できます。携帯電話会社の5Gとは完全に独立しているため、外部の通信状況に影響されません。
組織が自社の敷地内に基地局と制御装置を設置します。工場や病院、学校などで、その組織だけが使える通信網を作れます。インターネットに接続せずに運用することも可能です。
そのため、機密性の高いデータを扱う用途や、安定した通信が必要な業務に適しています。
5Gの基本特徴
ローカル5Gを理解するために、まず5G技術全般の特徴を把握しておきましょう。5Gには大きく分けて3つの特徴があります。
・超高速通信(eMBB)
・超低遅延(URLLC)
・多数同時接続(mMTC)
これらの特徴により、従来の通信技術では実現できなかったさまざまなサービスが可能になります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
超高速通信
超高速通信とは、従来の4Gと比較して理論上約20倍の通信速度を実現する技術です。
理論値では最大20Gbpsの通信速度が可能とされていますが、実際の通信速度は利用環境、接続機器数、電波状況等により大きく変動します。4Gでは時間がかかっていた大きなファイルのダウンロードも、条件が整えば格段に短時間で完了します。
この高速通信により、4K・8Kといった高画質映像のリアルタイム配信が可能になります。また、VRやARを使った体験サービスも、遅延なくスムーズに利用できます。製造業では、高精細なカメラ映像を使った品質検査システムなどにも活用されています。
超低遅延
超低遅延とは、通信の遅れ時間を理論上1ミリ秒以下まで短縮する技術です。
4Gでは約10ミリ秒だった遅延時間が、5Gでは理想的な条件下で1ミリ秒以下の実現を目指しています。
これは人間が反応する時間よりもはるかに短い時間です。
この特徴により、リアルタイム性が重要な用途での活用が可能になります。例えば、建設機械の遠隔操作や手術支援ロボットの操作などで威力を発揮します。また、自動運転車同士の通信や、工場での精密な機械制御にも欠かせない技術です。
多数同時接続
多数同時接続とは、1平方キロメートルあたり100万台のデバイスを同時に接続できる技術です。
4Gでは1平方キロメートルあたり約10万台が限界でしたが、5Gでは10倍の接続数を実現できます。これにより、IoT機器が大量に配置された環境でも安定した通信が可能になります。
この特徴は、スマートシティやスマートファクトリーの実現に重要な役割を果たします。例えば、工場内の数千台のセンサーや、街中の交通信号機、防犯カメラなどを同時に接続できるため、効率的な管理と制御が可能になります。
注目される背景
ローカル5Gが注目される理由は、企業のデジタル化が進んでいるからです。
工場では、機械同士をネットワークでつないで効率を上げる取り組みが広がっています。従来のWi-Fiでは電波が届く範囲や安定性に限界があったため、より高性能なローカル5Gが求められています。
また、コロナ禍で非接触での作業が重要になりました。病院での遠隔診療や、工事現場での遠隔操作など、さまざまな場面でローカル5Gの活用が期待されています。
さらに国もローカル5Gの普及を積極的に支援しており、導入しやすい環境が整ってきていることも注目される理由のひとつです。
ローカル5GとWi-Fi・他通信技術との違い

ローカル5Gを正しく理解するには、他の無線通信技術との違いを比較することが重要です。
特に、Wi-Fi・パブリック5G・プライベート5Gといった選択肢との違いを把握することで、ローカル5Gの立ち位置が明確になります。
通信技術の比較表(ローカル5G/Wi-Fi/他)
まずは、主要な通信技術ごとの特徴を比較表で確認しましょう。
| 項目 | ローカル5G | Wi-Fi | パブリック5G | プライベート5G |
| 運営主体 | 企業・自治体 | 企業・個人 | 通信キャリア | キャリア又は企業 |
| 利用範囲 | 敷地内限定 | 施設内限定 | 全国規模 | 契約範囲 |
| 通信範囲 | 敷地内広範囲 | 施設内狭範囲 | 全国 | サービス範囲 |
| セキュリティ | 高い(SIM認証) | 低い(パスワード) | 中程度(SIM認証) | 高い |
| 免許 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 初期費用 | 高額 | 安価 | 端末・契約費用 | 中程度 |
| カスタマイズ | 自由度高い | 制約あり | 不可 | 制限あり |
この表からは、ローカル5Gが他の通信手段と比べて、運営主体や利用範囲、セキュリティの面で大きく異なることがわかります。
次項では、各技術ごとの違いをさらに詳しく見ていきましょう。
Wi-Fiとの違い
ローカル5GとWi-Fiの最大の違いは、通信範囲とセキュリティです。
Wi-Fiは建物内の限られた範囲でのみ利用できますが、ローカル5Gは敷地内の広範囲をカバーできます。工場全体や屋外エリアなど、Wi-Fiでは電波が届かない場所でも安定した通信が可能です。
セキュリティ面では大きな差があります。Wi-FiはSSIDとパスワードによる認証のため、セキュリティリスクが存在します。一方、ローカル5GはSIM認証を使用し、閉域ネットワークとして運用できるため、より高いセキュリティを確保できます。
また、ローカル5Gは無線免許が必要で初期費用も高額ですが、Wi-Fiは免許不要で比較的安価に導入できるという違いもあります。
パブリック5Gとの違い
ローカル5Gとパブリック5Gの最大の違いは、運営主体と利用範囲です。
パブリック5Gは通信キャリアが運営し、全国規模で不特定多数の人が利用します。一方、ローカル5Gは企業や自治体が自ら免許を取得して運営し、敷地内の限定エリアでその組織だけが利用できます。
通信の安定性も大きく異なります。パブリック5Gは多くの人が同時に利用するため、混雑時には通信速度が低下する可能性があります。ローカル5Gは専用ネットワークのため、いつでも安定した通信品質を維持できます。
また、カスタマイズ性においても違いがあります。ローカル5Gでは、組織のニーズに合わせて通信設定を自由に調整できますが、パブリック5Gではそのような調整はできません。
プライベート5Gとの違い
ローカル5Gとプライベート5Gの違いは、提供形態と定義の違いにあります。
プライベート5Gは定義が曖昧で、通信キャリアが企業向けに専用ネットワークを提供する場合と、企業が主体となって構築する場合があります。一方、ローカル5Gは企業や自治体が自ら無線免許を取得し、完全に独立したネットワークを構築します。
運用面でも違いがあります。キャリア提供のプライベート5Gでは、企業は自分で基地局を設置する必要がなく、初期費用を抑えられます。ローカル5Gは初期費用は高額ですが、完全に自社管理できるため、長期的な運用コストや自由度の面でメリットがあります。
また、カスタマイズの自由度においても差があります。ローカル5Gは完全に自社管理のため、細かな設定変更が可能ですが、キャリア提供のプライベート5Gは提供会社の制約を受ける場合があります。
ローカル5Gのメリット・デメリット
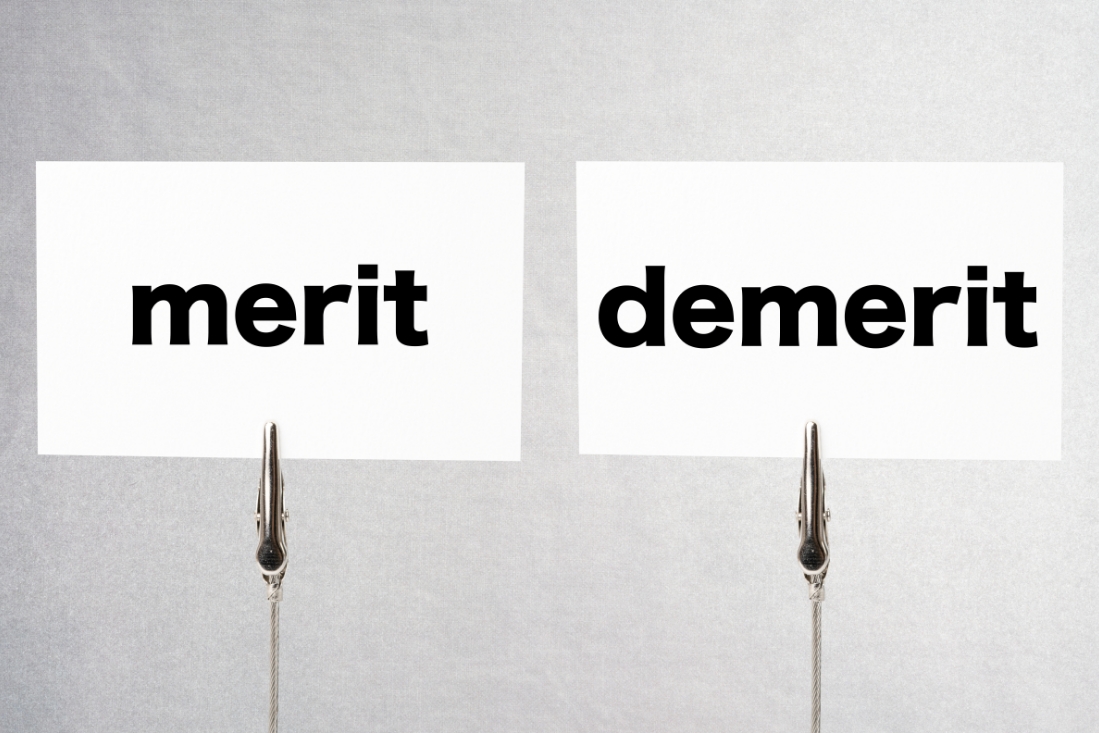
ローカル5Gの導入を検討する際は、メリットとデメリットを正しく理解することが重要です。高い性能とセキュリティを実現できる一方で、コストや端末の制約もあります。
ローカル5Gのメリット・デメリットについて、下記のポイントで解説していきます。
| メリット | デメリット |
|
・高速大容量通信 ・セキュリティ強化 ・広域エリアカバー ・速度比率カスタマイズ |
・高い構築・運用コスト ・対応端末の限定性 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4つのメリット
ローカル5Gには大きく4つのメリットがあります。
・高速大容量通信
・セキュリティ強化
・広域エリアカバー
・速度比率カスタマイズ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
高速大容量通信
ローカル5Gの最大のメリットは、理論上4Gの約20倍の高速通信が可能なことです。
適切な環境下では大容量データの送受信を高速で行えるため、製造業では高精細な検査映像をリアルタイムで伝送することが期待できます。
また、複数のデバイスが同時に通信しても速度低下しにくく、工場内の多数のカメラやセンサーでも安定した通信を維持できます。この特徴により、IoTシステムの大規模展開やAIを活用したリアルタイム分析が可能になります。
セキュリティ強化
ローカル5Gは専用の閉域ネットワークとして構築できるため、外部からの不正アクセスリスクを大幅に削減できます。
SIM認証により許可された端末のみが接続でき、インターネットに接続せずに運用することも可能です。機密性の高いデータを扱う研究開発や重要インフラの制御システムでも安心して利用できます。このセキュリティの高さにより、金融機関や政府機関の厳格な要件も満たせます。
広域エリアカバー
ローカル5Gは、Wi-Fiと比較して格段に広い範囲をカバーできます。
Wi-Fiが建物内の限られたエリアであるのに対し、ローカル5Gは工場の敷地全体や大規模施設全体をカバーできます。屋外エリアでも安定した通信が可能で、建設現場や農場での活用も期待できます。障害物による電波の減衰も少ないため、複雑な構造の建物内でも安定した通信を維持し、施設全体での統合的なシステム運用が実現できます。
速度比率カスタマイズ
ローカル5Gでは、業務内容に応じて上り下りの通信速度比率を自由にカスタマイズできます。
監視カメラシステムなど上り通信が多い用途では上り速度を重視し、映像配信など下り通信が多い用途では下り速度を重視した設定に変更できます。このカスタマイズにより、限られた通信容量を効率的に活用でき、コストパフォーマンスの向上も期待できます。業務の変化に応じて設定変更も可能なため、柔軟な運用が実現できます。
2つのデメリット
ローカル5Gには大きく2つのデメリットがあります。
・高い構築・運用コスト
・対応端末の限定性
それぞれ詳しく見ていきましょう。
高い構築・運用コスト
ローカル5Gの最大のデメリットは、構築と運用にかかる高額なコストです。
免許取得費用、基地局や制御装置の購入費用、設置工事費用など、初期投資は規模や用途により大きく異なりますが、一般的に高額な投資が必要とされています。
また、システム保守や電力費用などの運用コストも継続的に発生し、専門知識を持つ技術者の確保や育成にもコストがかかります。小規模な企業では費用対効果を慎重に検討する必要があります。
対応端末の限定性
ローカル5Gを利用するには対応端末が必要ですが、選択肢が限られているのが現状です。
一般的なスマートフォンやタブレットでは、ローカル5Gの周波数帯に対応していない機種が多数あります。そのため専用端末を新たに調達する必要があり、追加コストが発生します。産業用途に特化した耐久性の高い端末はさらに選択肢が限られており、既存システムとの連携を考慮すると端末選定に制約が生じる場合もあります。
ローカル5Gの導入事例と活用状況

ローカル5Gはさまざまな業界で実際に導入が進んでおり、それぞれの業界特性に応じた活用が行われています。
ユアサ商事グループは総合力を発揮し「モノづくり」「すまいづくり」「環境づくり」「まちづくり」の4つのフィールドに挑んでおり、海外・グリーン・デジタル分野についてはグループ全体で推進しています。
他にも、ローカル5Gの導入事例と活用状況について、下記の5つの業界で解説していきます。
・製造業での活用
・物流業での活用
・農業での活用
・医療分野での活用
・スタジアム・イベント会場での活用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
製造業での活用
NECプラットフォームズは、通信関連機器などを生産する掛川事業所でNECグループ内ではじめてローカル5Gを本格導入しました。2023年8月より新工場が稼働を開始しています。
地域共有型ローカル5GシステムによるAI異常検知等の実証も行われており、AIにより工場設備の異常検知や完成した部品の検品業務、スマートグラスを用いた遠隔指導、作業支援が実現されています。これにより技術伝承や生産性向上が図られました。
サミットスチール株式会社では、帯鋼(コイル)の各種加工を担うスチールサービスセンター事業でローカル5Gを導入し、商品(コイル)の傷の自動検出と遠隔地からの品質チェックの実現を目指しています。
物流業での活用
岡谷鋼機株式会社は2024年7月にNTT東日本との間でローカル5Gに関する提携契約を締結し、NTT東日本のマネージド・ローカル5Gサービス「ギガらく5G」を販売パートナーとして企業に提供しています。
自動搬送ロボットや無人フォークリフトの遠隔制御により、24時間稼働の無人倉庫を実現できます。商品の入出庫管理では、バーコードやRFIDタグの高速読み取りにより、リアルタイムでの在庫管理が可能になります。
農業での活用
東京都農林総合研究センターでは、2020年4月より東日本電信電話株式会社、株式会社NTTアグリテクノロジーと連携協定を締結し、ローカル5Gとスマートグラス等の先端機器を活用した遠隔農作業支援の実証を進めています。
4K定点カメラを複数台設置して農地の状況を遠隔で確認し、死角になる場所は遠隔操作が可能な移動式カメラによって確認します。農地に未経験栽培スタッフを派遣し、カメラが搭載されたスマートグラスを着用してもらい、センターの研究員が遠隔で農作業支援を実施しています。
高知県では、株式会社NTTデータ経営研究所を代表機関として11機関がローカル5Gを用いたゆず生産の効率化と生産者の確保・育成をめざすスマート農業実証プロジェクトを2022年8月より開始しています。
医療分野での活用
聖マリアンナ医科大学やNTTドコモなど4者コンソーシアムによる実証実験では、病院内にローカル5G環境を構築し、多数対多数の高精細映像伝送やAIを活用したX線画像診断などの検証が行われました。
院内をストレッチャーで移動する救急患者の映像を撮影し、別の場所にいる医師のタブレットへ5Gでリアルタイム配信する検証も行われています。これにより医療行為を行えないスタッフだけで患者の移動を安全に行うことができます。
NTTコミュニケーションズでは、令和5年度に複数の消防本部と複数の搬送先病院との映像・バイタルの遠隔連携、および複数の2次救急病院と複数の3次救急病院との遠隔連携の接続検証を5つの病院と3つの消防本部において実施しています。
スタジアム・イベント会場での活用
長野県では、プロバスケットボールチーム「信州ブレイブウォリアーズ」のホームアリーナであるホワイトリングに、国内初の産官による商用ローカル5Gシステムを導入しています。
通信環境の改善を行い、電子決済、モバイルオーダー及びモバイルチケッティングが滞りなく使用できる環境構築を実施し、大型ビジョン(映像伝送)、LED照明コントロールおよびゲームクロックの無線化を実施しています。
株式会社ミクシィでは、スポーツビジネスにおいてローカル5Gを選択し、これまでにない映像配信の取り組みを進めています。来場者はVRやARを使った新しい観戦体験を楽しめ、選手の詳細データや多角度映像をリアルタイムで配信する従来にない臨場感のあるエンターテインメントを提供しています。
ローカル5Gの免許取得

ローカル5Gを利用するためには、必ず無線局の免許を受ける必要があります。ローカル5Gの導入に際しては、総務省はガイドライン(本紙及び付録)を示しております。
ローカル5Gの免許取得について、下記の3つのポイントで解説していきます。
・免許取得の条件
・申請の流れと手続き
・審査期間と注意点
それぞれ詳しく見ていきましょう。
免許取得の条件
ローカル5Gの免許を取得するには、下記の条件を満たす必要があります。
・利用場所の区分(自己土地利用・他者土地利用)
・周波数帯の選択(4.5GHz帯・28GHz帯)
・免許申請主体の制限
ローカル5Gには、その利用場所ごとに、その利用形態に応じて、「自己土地利用」・「他者土地利用」が制度上規定されています。自己土地利用とは、自己の所有する土地又は建物内に限り、他のローカル5G無線局からの混信に対して、保護を求めることができる利用形態です。
ローカル5Gの周波数帯には、サブ6といわれる4.5GHz帯及びミリ波といわれる28GHz帯の2つがあります。利用目的や環境に応じて適切な周波数帯を選択する必要があります。
また、2025年1月時点において、全国でモバイルサービスを提供している特定事業者(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、UQコミュニケーションズ、Wireless City
Planning等)は、ローカル5Gの免許を取得できない制限があります。ただし、これらの事業者の子会社は免許を取得できます。
※制度は変更される可能性があるため、申請前に必ず総務省の最新情報をご確認ください。
参考:総務省電子利用ポータル|ローカル5G
申請の流れと手続き
ローカル5Gの免許申請は、下記のステップで進める必要があります。
参考:総務省電子利用ポータル|登録
ステップ1:事前の干渉調整
開設を希望する場所の近隣にローカル5G無線局を開設している免許人がいる場合は干渉調整が必要な場合がありますので、まずはカバーエリア図等を作成の上、総合通信局等にご確認をお願いします。
既存のローカル5G局との電波干渉を避けるため、事前の調査と調整が必要です。確認の結果、他の免許人との干渉調整が必要な場合は、干渉調整を実施の上で、免許申請をしていただくようお願いします。
ステップ2:必要書類の準備
申請書、無線局事項書、工事設計書は、総務省の「電波利用ホームページ」でダウンロードできます。これらの書類を正確に作成し、技術的条件を満たすことを証明する必要があります。
また、利用予定のスマートフォンやモバイルWi-Fiルーターなどの端末も、機種や台数を報告して、免許申請しなければなりません。
ステップ3:総合通信局への申請
必要な書類作成が終われば、管轄の総合通信局へ提出します。総合通信局が提出した書類をもとに、審査基準に合致しているかどうかを審査します。
申請は各地域の総合通信局に対して行います。
審査期間と注意点
免許申請後の標準的な処理期間は約1ヵ月半です。導入スケジュールを策定する際は、この審査期間を必ず考慮する必要があります。
免許申請と並行して、自社でローカル5Gを構築する場合は「999002」から始まる利用者識別番号を取得します。取得申請先は、総務省
総合通信基盤局電波部移動通信課です(2025年1月時点)。申請から取得までの期間は状況により変動するため、事前に担当部署へ確認の上、計画的な申請が必要です。
また、ローカル5Gガイドラインの「2.(10)無線局の免許が交付された後の手続(P.14~15)」をご確認ください。免許取得後も定期的な報告や更新手続きが必要になるため、継続的な管理体制の構築が重要です。
参考:総務省電子利用ポータル|ローカル5G
ローカル5Gの導入方法

ローカル5Gの導入は、免許取得から実際の運用開始まで段階的なプロセスを踏む必要があります。
ローカル5Gの導入方法について、下記の4つのステップで解説していきます。
・ステップ1:導入計画の策定
・ステップ2:システム設計と機器選定
・ステップ3:構築・設置作業
・ステップ4:運用開始と保守管理
それぞれ詳しく見ていきましょう。
参考:総務省電子利用ポータル|ローカル5G導入に関するガイドライン
ステップ1:導入計画の策定
まずは、導入目的と解決したい課題を明確にします。そして、利用エリアと通信要件を定義します。
ローカル5Gは初期の環境構築に高額な投資が必要です。導入規模(カバーエリア、基地局数等)、利用用途、求める性能により費用は大きく変動するため、具体的な費用については専門業者への相談が不可欠です。そのため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
免許申請期間(約1ヵ月半)を含めた全体スケジュールを策定します。
ステップ2:システム設計と機器選定
次に、技術要件に基づいて周波数帯を選択します。そして、基地局配置とカバーエリアを設計します。
直進性が高く、廊下の曲がり角や物陰などで電波が届かない不感地帯が生じてしまうという課題に対しては、電波を反射する反射板を設置し、必要な場所を漏れなくカバーできるように5Gエリアを構築する必要があります。
機器選定では、一体化された製品を選択することで構築期間の短縮が可能です。専用端末の調達も並行して進めます。
ステップ3:構築・設置作業
免許取得後、承認された設計書通りに機器設置を実施します。接続作業を行います。
自社でローカル5Gを構築する場合は「999002」から始まる利用者識別番号の取得が必要です。SIM調達も並行して進めます。構築完了後は、通信テストと性能検証を実施します。設計通りの性能を確認します。
ステップ4:運用開始と保守管理
運用体制の確立と利用者教育を行います。システム運用を開始します。
まだまだ新しい技術であるため、維持費がいくらかかるか読みづらいところが難しい部分となります。実際に導入を検討される場合は、既に免許を取得しており専門知識も豊富な専門の業者に相談することが推奨されます。
免許取得後も定期的な報告義務があります。継続的な管理体制の維持が重要です。
まとめ:ローカル5G導入で知っておくべきポイント
ローカル5Gは、企業や自治体が独自に構築する専用の5Gネットワークです。Wi-Fiやパブリック5Gと比較して、高いセキュリティと安定した通信を実現できます。一方、高額な初期投資と専門知識が必要という課題があります。
現在、製造業、物流業、農業、医療分野、スポーツ施設などで実際の導入事例が生まれています。工場の自動化や遠隔医療、農作業支援などで成果を上げています。
導入には総務省からの無線局免許取得が必須です。審査期間は約1ヵ月半を要します。導入プロセスは計画策定から運用開始まで4つのステップに分かれます。各段階で専門的な知識と経験が求められます。
ユアサ商事のような専門商社は、350年以上の歴史と豊富な実績を活かしています。顧客企業のローカル5G導入を総合的にサポートできます。高額な投資を伴うローカル5G導入を成功させるには、専門知識を持つ信頼できるパートナーとの連携が重要です。
